“現場のリアル”にこそ寄り添う勤怠管理。建設業にフィットするRocoTimeの実力
2025/8/26

現場を止めずに、働き方を見直すために。建設業の勤怠管理は独特です
建設業界では、「勤怠管理」のあり方が他業界とは大きく異なります。オフィスに出社し、PCを立ち上げ、定時に打刻する―。そのような働き方を前提とした勤怠システムでは、建設業界の現場にはなじみません。
毎朝異なる現場へ直行し、作業が終わればそのまま帰宅する。現場ごとにルールや労務条件が違い、打刻も日報も紙ベース。こうした「建設業の現場ならではの勤怠のリアル」は、システム化・デジタル化が難しい理由としてたびたび挙げられてきました。しかし2024年問題(時間外労働の上限規制)をはじめ、業界を取り巻く労務環境は大きく変わりつつあります。法令遵守、施工体制台帳との連携、工数や原価の正確な把握―。
「勤怠」は今や、単なる出退勤の記録ではなく、業務全体の信頼性を左右する中核情報としての役割を担いはじめています。
1. 直行直帰、紙の台帳、バラバラのルール。それでも回ってきた現場
建設・土木業界の勤怠管理は、常に「現場の事情優先」で運用されてきました。
従業員は現場に直行し、紙の台帳に手書きで出勤時刻を記入。退勤時には口頭で報告を受けたり、日報にまとめたりと、属人的なやりとりで処理されてきたのが実情です。また現場ごとに作業時間や休憩時間の慣習が異なり、同じ会社内でもルールが統一されていないことも珍しくありません。たとえばある現場では7時30分始業、別の現場では8時15分開始というように、「現場単位の就業文化」が勤怠ルールのベースになっているケースも多くあります。
それでもこれまで業務が回ってきたのは、管理者や作業員が現場ごとのルールを“経験と勘”でうまく吸収してきたからです。裏を返せば、勤怠という重要な労務情報が、個人の裁量と現場任せの判断に依存してきたとも言えます。
2.「管理される」ではなく「支えてくれる」勤怠システムとは?
現場に合わない勤怠管理システムは、導入しても定着しません。多くのシステムは「企業全体でルールを統一し、従業員の働き方をシステムに合わせる」ことを前提に設計されています。しかし建設業界の現実はその逆です。重要なのは、多様な現場の事情に合わせて柔軟に対応できる仕組みであること。勤怠管理のシステムは「現場を管理する道具」ではなく、「現場が混乱しないよう支えてくれる存在」であるべきです。
働き方が多様化し、法的責任も厳しく問われる今、勤怠管理を「守りの仕組み」として再設計することが急務となっています。
そしてその第一歩は、建設業界の現場に本当にフィットするシステムを選ぶことから始まります。勤怠管理システム RocoTimeは、まさにその“現場に寄り添う”ための仕組みを提供できるシステムです。
勤怠管理システム
「働き方改革」時代の勤怠管理
日本の商習慣を網羅したクラウド 柔軟対応でカスタマイズできる!
なぜ、建設業の勤怠管理は「一般的な仕組み」ではうまくいかないのか?

「勤怠管理システム」と聞くと、多くの人が「事務所への出社・退社を記録するもの」「PCやスマートフォンから定時に打刻するもの」といった運用を思い浮かべるかもしれません。しかし建設業界における勤怠管理は、そのような一般的な仕組みとは大きく性質が異なります。出退勤のルールが現場によって異なり、打刻の手段も紙・口頭・日報など多様です。さらに工期や安全管理、施工体制台帳との整合など、他業界にはない複雑な要件が求められる点も特徴です。
ここでは建設土木業界に特有の構造課題を7つの視点から整理し、「なぜ一般的な勤怠管理システムではうまく機能しないのか」を明らかにしていきます。
1. 直行直帰・複数現場移動が常態化している
建設会社の多くでは、作業員が毎日決まった事務所に出社するわけではありません。実際の勤務は現場単位で行われ、出勤・退勤はそれぞれ異なる場所で発生する「直行直帰型」が一般的です。また1日に複数現場を移動する職種もあり、ひとつの場所で働くという前提自体が成り立たないケースもあります。
このような勤務形態に対し、「オフィスに設置された打刻機を使う」「決まった場所でアプリから打刻する」といった仕組みでは、正確な勤怠データを取得することが困難になります。
現場にWi-Fiがなかったり、移動中に通信が途切れたりするなど、インフラ環境の制約も現場では頻繁に起こります。また、現場での作業開始時刻や終了時刻が変動することも多く、「あらかじめ決めた時間帯に打刻すればよい」という固定観念も通用しません。結果として、正確な出退勤の把握ができず、紙や口頭での補完が常態化している現場も少なくないのが実情です。
この課題に対応するには、位置情報や打刻方法に柔軟性を持たせ、直行直帰でも問題なく記録できる設計が求められます。
単に「勤怠を記録する」だけでなく、移動を含めた働き方そのものを前提にした仕組みがなければ、実運用には耐えられません。
2. 現場ごとに労働慣習・契約条件が異なる
建設業界では、同じ会社に所属していても、現場によって勤務時間・休憩時間・残業ルールがまったく異なるというケースが一般的です。
たとえば、ある現場では7時半始業・17時終業、別の現場では8時開始・16時終了というように、就業時間帯そのものが現場の都合で決まることが珍しくありません。さらに、休憩の取り方も現場の慣習に左右されるほか、契約形態も社員・日雇い・外注など多様に混在しています。これらの条件が統一されていない中で、一律のルールに基づいた勤怠管理を行うことは、実質的に不可能です。
一般的な勤怠管理システムでは、「企業内で就業ルールを標準化した上で、それを全従業員に適用する」ことを前提として設計されているため、建設業のような“マルチルール運用”が前提の現場環境には適応しにくいのが現状です。結果として、
- 現場ごとにExcelや紙での勤怠記録を別管理
- システム側で一部の例外処理を手作業で補完
- 勤怠締め時に手計算・確認作業が発生
といった運用負荷が人事・労務担当にのしかかり、ミスや集計遅延の原因にもなっています。
このような現場の多様性に対応するには、勤怠ルールを「一括で統一」するのではなく、「複数のルールを前提に吸収できる」設計思想が不可欠です。
ルールをシステムに合わせるのではなく、システムを現場の運用に柔軟に適合させることが、建設会社の勤怠管理では求められます。
3. 紙文化が根強く、施工台帳・労務日報との連動が必要
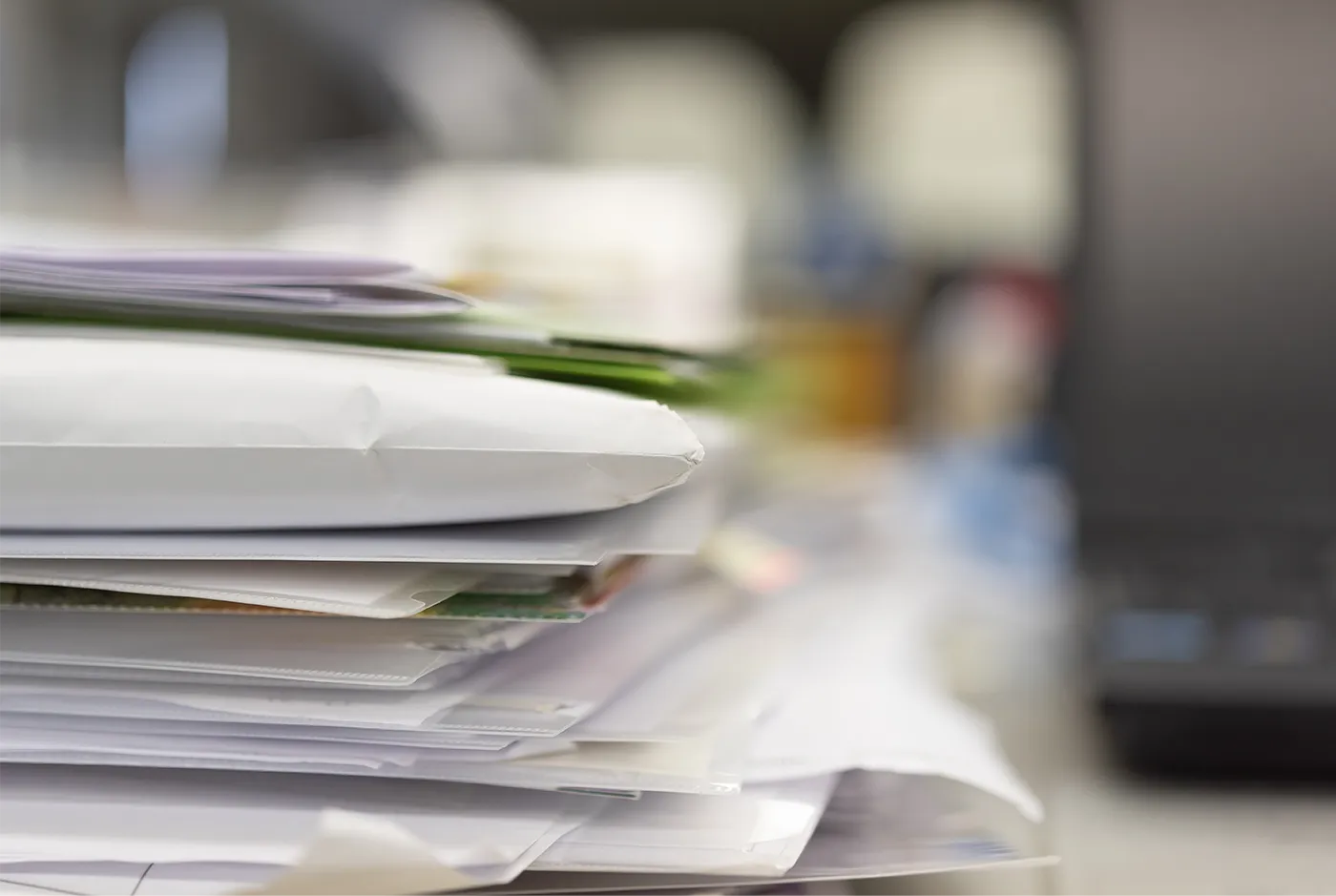
建設会社における勤怠管理は、紙を中心とした運用が多く残っているのが実情です。出勤簿、作業日報、現場ごとの労務報告、これらが手書きで作成・回収される現場も少なくなく、いわゆる「台帳文化」が根強く残っています。この背景には、公共工事を含む多くの現場で提出を求められる「施工体制台帳」や「作業員名簿」といった法定書類の存在があります。
これらの書類には、「誰が、いつ、どの現場に配置されたか」という情報を正確に記録する義務があり、勤怠情報と現場配置記録との整合性が担保されなければ、監査対応や契約トラブルの原因になりかねません。しかし多くの勤怠管理システムは、これらの台帳と連携する前提では設計されていません。
結果として勤怠データとは別に紙の台帳を作成したり、作業日報をもとに手作業で台帳を補完したりと、二重管理や転記作業が日常化している現場が多く存在しています。
さらに問題なのは、勤怠情報と作業実績が分断されていることで、後から矛盾が見つかるケースがあるという点です。たとえば、勤怠システムでは8時出勤と記録されている一方で、台帳では7時半現場入りとなっている―。
こうした乖離が生じると、工事受注者としての信頼性や法令順守の観点から、深刻なリスクとなります。建設業界では単なる勤怠記録だけでなく、「施工体制台帳・労務日報との連携を前提とした勤怠情報の整備」が欠かせません。
この点を軽視した勤怠システムでは、現場に定着しないばかりか、法務・監査対応において致命的な弱点となる可能性があります。
4.「工期厳守」が第一優先で、勤怠管理が後回しになりやすい
建設業界において、最も強く意識されるのが「工期の遵守」です。契約上の納期が絶対であり、工程が少しでも遅れれば、その後の工種や協力会社全体に影響を及ぼすため、あらゆる判断が工期優先で行われるのが現場の常識です。その結果として、勤怠管理や労務手続きといった「管理系の業務」は、どうしても後回しにされがちです。
現場では進捗確認、安全対策、資材の受け入れ、人員配置など、日々変化するタスクに追われており、勤怠の打刻漏れや申請忘れが常態化している現場も少なくありません。また、作業終了後に現場責任者が打刻状況を確認し、事後で補正・追加入力するという運用も散見されます。こうした運用では、勤怠データが本来の実態とずれてしまうリスクが高く、「あとで整える」ことが習慣化することで、制度自体の形骸化を招きます。
申請・承認フローが複雑なシステムを導入している場合、現場からは「管理のために現場が止まる」「余計な仕事が増える」といった不満が出やすく、結果として運用そのものが形だけになってしまうこともあります。建設会社にとっては、現場の作業が止まらないことが最優先事項である一方で、法令遵守や勤怠の正確性も問われる時代になっています。
この両立を図るには、現場の負担を増やすことなく、自然な流れで正確な勤怠を記録できる仕組みが必要不可欠です。
5. ITリテラシー・機器利用環境の差が大きい
建設現場では、作業員や現場管理者の年齢層やITスキルに大きな差があります。若手の作業員はスマートフォンやアプリの操作に慣れている一方で、年配の職人や協力会社のスタッフの中には、ICカードやパスワードの扱いにすら抵抗を示すケースも少なくありません。
また現場の環境自体もIT化に適していない場合があります。たとえば、仮設事務所にはWi-Fiが通っていない、山間部では通信が不安定、充電環境が整っていない―といった状況は珍しくありません。
このような現場では、「PCやタブレットでWeb打刻」「スマホで打刻」といった標準的な勤怠管理の運用が成立しづらくなります。その結果として、
- 一部の従業員だけが打刻できず、管理側が代理入力する
- 日報や紙打刻に逆戻りする
- システム導入が現場の混乱を招く
といった問題が発生し、「結局、現場には合わなかった」という理由で勤怠管理システムが形骸化してしまう事例もあります。
建設会社が勤怠管理システムを導入する際には、ユーザー全員が「自分ごと」として自然に使える仕組みであることが欠かせません。そのためには、操作のシンプルさだけでなく、現場のIT環境や利用者のスキル差を前提とした複数の打刻手段(ICカード、QRコード、顔認証、紙との併用など)を用意できる柔軟性が求められます。
「誰にとっても、使いやすい」―それが、建設土木業界における勤怠管理システムの基本要件と言えます。
6. 勤怠データが「原価管理の武器」になり得るが、実際は活用されていない

建設会社にとって「労務費」は工事原価の中でも大きな割合を占める要素です。本来であれば、作業員ごとの労働時間を正確に把握することは、プロジェクト単位での原価管理や利益率の分析に直結する重要なデータ資源となるはずです。しかし実際には、勤怠データがそのまま原価計算や工数分析に活かされていない企業が多く見られます。原因としては、以下のような構造的な課題が挙げられます。
- 勤怠情報と工事案件の紐づけができていない
- 拠点単位・部門単位でしか工数を集計していない
- 各現場の勤怠データが紙やExcelで個別管理されている
- 工数集計のために別システムや手計算を併用している
このような状況では、過去の案件における労務負荷や人員配置の傾向を把握することができず、見積精度の向上や収益性改善の機会を逸してしまいます。さらに工期中に「人件費がどこまで膨らんでいるか」「稼働実績に対して予定との差異はどうか」といったリアルタイムなコスト把握ができないことで、問題の発見が工事終了後になってしまい、手遅れの赤字案件が発生するリスクもあります。
勤怠情報は単なる出退勤の記録にとどまらず、プロジェクト原価管理・人員配置戦略・業務効率化の判断に資する「経営資源」であるべきです。しかし、これを活用するためには、勤怠データが集めやすく・整理しやすく・紐づけやすい状態で存在している必要があります。
一般的な勤怠管理システムでは、「勤怠を記録する」こと自体は可能でも、工数や原価への連携設計が欠如している場合が多く、活用できないデータ、いわば“死んだ数字”になってしまっているのが実情です。建設業における勤怠データは、正しく活用されて初めて利益を生み出す力を持つ―。その前提に立った運用設計が求められています。
7.「施工体制台帳」や「安全衛生書類」への対応が特殊
建設業界における勤怠管理は、単に労働時間を記録・集計するだけでは完結しません。
現場で働く作業員の勤務実績は、「施工体制台帳」や「作業員名簿」「安全衛生書類」など、法令や発注者に提出が求められる各種帳票と密接に関係しています。
たとえば公共工事では、作業員の配置状況を日ごとに記録・提出する義務があります。このとき台帳に記載された内容と、勤怠システムに記録された出勤情報が矛盾していれば、発注者からの指摘や是正要求につながるリスクがあります。さらに元請企業としては「誰がいつ現場にいたか」を明確に証明できる仕組みを持つことが、労災リスク・監査対応・入退場管理の観点からも重要になっています。
近年では現場の入退場履歴をICカードや顔認証で記録し、勤怠情報と紐づける動きも広がりつつあります。しかし一般的な勤怠管理システムはこうした建設業界特有の書類要件や現場運用を想定していないことが多く、
- 台帳フォーマットへの出力ができない
- 証明力が不十分で信頼性を担保できない
- 現場単位での情報抽出が難しい
といった課題を抱えたまま、部分的な導入にとどまってしまうケースも見られます。
建設会社にとって重要なのは、勤怠情報が「現場にいた証拠」として通用する形式で記録・保存されていることです。そしてその情報を、施工体制台帳や各種管理書類と連動させて出力できる仕組みがなければ、日々の現場管理と法令対応の両立は難しくなります。
「勤怠」と「証明性」―この2つを同時に成立させることこそ、建設業界における勤怠システムの必須条件と言えるでしょう。
勤怠管理システム
「働き方改革」時代の勤怠管理
日本の商習慣を網羅したクラウド 柔軟対応でカスタマイズできる!
RocoTimeなら、建設業の現場でも“しっかりと回る”勤怠管理ができる

直行直帰、現場移動、紙台帳、複雑な就業ルール。建設業における勤怠管理が「一般的な仕組みではうまくいかない」ことは、ここまで述べてきた通りです。
では、どうすればいいのか。その答えのひとつが、勤怠管理システム RocoTimeです。
RocoTimeは、業種・業態ごとに異なる運用に対応するために、500以上の設定項目と高い拡張性を備えたクラウド型勤怠管理システムです。特に建設業界においては、以下のような業界特有の要件に対し、個別最適ではなくシステムとして吸収できる柔軟性が評価されています。
- 複数現場・直行直帰対応(GPS打刻・顔認証・スマホ打刻)
- 現場単位・契約単位で異なる就業ルールを個別設定
- 施工体制台帳や労務日報との整合性確保
- 工数管理・原価連携・帳票出力対応
- 紙文化やITリテラシー差への対応策も含む多彩な打刻手段
これまで「現場が合わせるしかなかった」勤怠管理の常識を、「現場に寄り添って吸収する仕組み」に変える。それが、RocoTimeが建設業界で選ばれている理由です。
ここからは建設業が直面してきた7つの構造課題に対して、RocoTimeがどのように実際の運用で解決していけるのかを、具体的にご紹介していきます。
1. GPS打刻・顔認証・スマホ対応で、直行直帰も正確に把握
建設業では、直行直帰や複数現場の移動が当たり前です。現場の始業・終業時間もまちまちで、全員が一カ所に集まって出勤打刻をするような運用はほとんどありません。
RocoTimeはそうした勤務実態に対応するために、3つの仕組みで「正確で無理のない打刻」を実現します。
● GPS打刻:現場の所在地を自動で記録
作業員がスマートフォンで打刻すると、その位置情報が自動で記録されます。これにより「どの現場で働いたのか」が勤務記録と一体化し、後から紙で補足する必要がなくなります。
- 管理者は、各打刻地点を地図上で視覚的に確認可能
- 午前と午後で異なる現場に入った場合でも、現場単位で勤務実績の入力が可能
- 担当者が口頭申告や紙に書き残す必要がなくなり、不正確さ・記録漏れ・集計ミスが激減
たとえば「午前は基礎工事、午後は外構工事」といった動きでも、現場ごとの稼働実績が明確に残るため、原価管理や施工体制台帳との整合性確保にも直結します。
● 顔認証打刻:なりすましや代理打刻を排除
本人確認を伴う「顔認証打刻」にも対応しています。スマートフォンや現場のタブレットで顔を読み取るだけで、本人確認と打刻が同時に完了します。
- なりすましや代理打刻を防止
- 顔データは各作業員に紐づき、ヘルメットや作業着姿でも認識可能
- 複数人が共用する現場端末でも、順番に立つだけで個別認証が完了する運用が可能
応援スタッフや日雇い作業員が多い現場でも、誰がどの時間帯にいたかを明確に管理できます。
● スマホ対応:どこからでも打刻できる
作業員は自身のスマートフォンから打刻が可能です。「出勤」「退勤」だけでなく「休憩開始・終了」も簡単に操作できます。
- 直行直帰時も、事務所に立ち寄らずに打刻が完了
- 機器設置のコスト不要。スマホ1台あれば打刻運用がスタート
仮設事務所・山間部・工区分散型の大規模現場でも、記録の欠損や補正が発生しません。
● 管理者にとっても手間のかからない勤怠記録に
- 打刻漏れ・不正のチェックが不要になる
- 代理申請や手入力が大幅に減る
- 現場別の集計がワンクリックで出力できる
正確な勤怠が「勝手に整う」状態が生まれることで、日常業務の負担が確実に軽減されます。
「どこで・誰が・どのくらい働いたか」が正確に残ることは、施工体制台帳、安全衛生書類、工事原価管理、労務コンプライアンス―すべての土台です。
RocoTimeはこの建設業の土台情報を、誰にでも簡単に・正確に・漏れなく記録できる仕組みとして提供しています。
2. 現場単位のルールを吸収する柔軟なパラメータ設計

建設業では現場や契約形態によって始業時刻・休憩時間・休日設定が異なるケースが多くあります。その違いを勤怠管理システム側で吸収できなければ、運用は結局アナログに逆戻りしてしまいます。
勤怠管理システム RocoTimeは、500以上の設定項目を備えており、各現場ごとのルールを制度的に構築可能です。
● 現場ごとの就業条件を設定だけで再現
以下のような複雑な就業条件でも、パラメータの組み合わせによって「ルールとして自動運用」できます。
| ケース | RocoTimeでの対応例 |
|---|---|
| A現場:7:30始業、B現場:8:00始業 | 勤務パターンを現場単位で切り分け設定可能 |
| 昼休憩時間が現場により異なる | 休憩開始・終了時刻を現場別に個別設定 |
| 特定の曜日のみ稼働(隔週日曜出勤など) | 曜日別勤務パターンにより対応可能 |
| 時間外の扱いが異なる現場(早出、残業等) | 時間帯別の割増率や上限時間をルールで制御可能 |
| 雨天順延・短時間勤務などの臨機対応 | 指定条件下での勤務時間の補正ルールを事前設定 |
現場がどれだけ多様でも、テンプレート化しておけば担当者は現場を選ぶだけで、正しい勤怠ルールが適用されます。
● 管理部門と現場、双方の負担を軽減
- 各現場の就業条件を一覧で管理可能
- パターンをコピー・流用できるため、新現場追加時の設定も簡易化
- 人手での補正や都度の問い合わせが大幅に減少
ルールを固めるのではなく、ルールを柔軟に扱える設計に変えることが、現場混乱の防止と勤怠精度の両立につながります。このように、RocoTimeは現場単位で異なる労務ルールを例外ではなく制度として取り込む構造を持つ勤怠管理システムです。
建設業に必要なのは、「画一化された運用」ではなく、「多様性を前提とした仕組み」です。
3. 紙・口頭・手作業に頼らない:台帳・日報との連携も視野に
勤怠データの整備が進まない要因のひとつが、施工台帳や労務日報など、紙ベースの業務との分断です。多くの現場では、実際の稼働状況は台帳や日報に記録され、勤怠とは別運用になっていることが少なくありません。こうした勤怠と現場記録の分離は、二重入力・手作業による転記・記録の齟齬といった、現場にも管理者にも無視できない負担とリスクをもたらしています。
RocoTimeは、こうした業界特有の紙文化や運用慣習にも柔軟に対応できる構造を持っています。
● 現場データと勤怠を「一元管理」する仕組み
RocoTimeでは、以下のような仕組みによって、勤怠と現場記録の分断を解消します。
- 申請時に現場名・作業内容を入力・選択
→ 「誰が・どの現場で・どんな作業をしたか」が記録される - 作業日報や労務日報に必要な項目をカスタマイズ登録可能
→ たとえば「工事種別」「協力会社名」「担当工程」等、帳票情報もRocoTime上に記録 - 現場別・日別・人別に整形されたデータをCSVで出力
→ 施工体制台帳や日報と内容を合わせるなど、カスタマイズレポートを設定可能
● 出力された勤怠データをそのまま現場帳票に活用できる
| 従来の運用 | RocoTime導入後 |
|---|---|
| 勤怠と日報を別々に記入 | 申請と同時に日報項目も記録可能 |
| 紙の台帳に手で転記・集計 | システム内で現場別に自動集計 |
| 入力ミスや記録の齟齬が頻発 | データは一元管理され齟齬を防止 |
| 日報・帳票作成に時間がかかる | お客様の帳票様式に合わせたカスタマイズレポートを作成可能 |
● 管理者・現場双方の実務がスムーズに
- 「紙に書いて、事務所にFAX」などの旧来の作業が不要に
- データの抜け・間違いが減り、帳票のチェック工数が大幅削減
- 協力会社の出勤管理や日報提出の回収作業もスピードアップ
RocoTimeなら、勤怠記録がそのまま“現場の記録”にもなるため、日報・施工台帳・体制書類と一貫した情報管理が可能になります。「勤怠と現場は別物」という意識から「勤怠が現場管理の起点になる」運用へと切り替えることで、業務の透明性と正確性、そして作業効率が飛躍的に向上します。
4.「工期優先」で後回しにされがちな勤怠管理を、止めずに仕組み化
建設業では、工期厳守が最優先事項とされる現場が多く、勤怠管理がどうしても後回しになりがちです。日々の進捗に追われ、申請・承認・集計といった勤怠関連の処理が滞る、あるいは属人化してしまうのは決して珍しいことではありません。
勤怠管理システム RocoTimeは、運用自体が「現場を止めない」設計になっているため、こうした現場主導・スピード優先の環境でも、ストレスなく勤怠管理を仕組みとして定着させることができます。
● 止めずに回る勤怠をつくる、3つの仕組み
| 運用の課題 | RocoTimeでの解決策 |
|---|---|
| 打刻漏れ、承認遅れ、未集計などが頻発 | 自動リマインド・アラート通知で抜けを防止 |
| 月末にまとめて処理し負荷が集中 | 日次単位での確認・申請がスマホで完結可能 |
| 承認フローが複雑で滞る | 所属・職位ごとの承認ルートを柔軟に設計可 |
● 勤怠処理のタイムラグをなくすことで、現場も管理側も楽になる
- 作業員は、日々の勤務をスマホ上でその場で申請・打刻できる
- 所長や職長は、現場にいながらスマホで承認・差戻しが可能
- 管理部門は、進捗の見える化で催促・確認のやりとりが減少
こうした仕組みの導入によって、月末だけが「忙しい日」ではなくなり、現場と管理の両方に平準化された勤怠運用が実現します。
● 急な応援・変更・早上がりにも即対応できる柔軟性
- 作業員が現場を移動する場合も、打刻データを現場単位で自動分割・集計
- 短時間勤務や早退も、設定ルール内で自動処理され手修正不要
- 応援勤務や協力会社の一時作業も、登録と記録が簡単に行える
RocoTimeは、「止めない現場」を前提に設計された勤怠管理システムです。そのため、現場作業を優先しながらも、勤怠の正確性・スピード・整合性を高水準で両立できます。工期を守るために“見て見ぬふり”されがちだった勤怠管理も、仕組みに任せることで「やらないからできない」から「自然にできている」状態へと変わっていきます。
5. 誰でも使えるUIと運用設計で、ITリテラシー格差も吸収

建設業の勤怠管理においては、利用者ごとのITリテラシーの差が運用の障壁になることがあります。現場では年齢層も幅広く、スマートフォンやPCの操作に慣れていない作業員が一定数存在するのが実情です。その結果、「打刻できない」「申請が分からない」「操作ミスが多発する」といった声が寄せられ、勤怠管理そのものが形骸化するリスクもあります。
勤怠管理システム RocoTimeは、こうした課題に対し「誰もが迷わず使えることを重視した設計」が施されています。打刻や申請といった基本操作はもちろん、管理者側の設定や承認も、直感的に扱えるよう設計されています。
● RocoTimeが現場でも使いやすい理由
| 課題 | RocoTimeの対応機能 |
|---|---|
| 高齢者・非IT層にとって操作が難しい | スマホ用に最適化された使いやすい設計 |
| スマホを持たない・使わない作業員もいる | ICカード打刻・PCブラウザ・紙ベース記録にも対応 |
| 申請や承認が複雑で混乱しやすい | 申請項目は必要最低限に絞り、設定も会社ごとに最適化可能 |
| 現場ごとに打刻方法が異なり混乱を招く | 拠点ごとに運用設計を切り替え可能(例:紙+スマホ/IC+PCなど) |
● 使う人に合わせて設計できる柔らかい運用
RocoTimeでは、システムを「人に合わせる」発想で設計されています。
たとえば以下のように、現場実情に応じた運用が可能です。
- スマホ打刻が困難な高齢作業員には、ICカード運用を用意
- PC、スマホを使えない現場には、本社担当者による代理入力機能の活用
- 外国人技能実習生には、言語選択機能から英語表示に簡単に切り替えて表示
このように、勤怠管理システム RocoTimeは「誰でも迷わず使えること」こそが正確な勤怠管理の第一歩であると捉え、UI(操作画面)と運用設計の両面から、「使えない人をつくらない」設計思想を徹底しています。結果として、「入力できない」「間違えた」「分からない」ことによる集計ミスや修正工数が減少し、現場も管理部門もストレスなく、勤怠業務を標準化できます。
6. 勤怠データを“原価の見える化”に変える仕組み
建設業では、労務費が工事原価の大きな割合を占めるにもかかわらず、実際の勤怠データが原価管理に活用されていない現場は少なくありません。作業日報や協力会社からの請求書に頼った集計では、精度が低く、タイムラグが大きいため、「どの現場で、誰が、何時間働いたのか」という実態をタイムリーに把握することが困難です。この“見えない原価”が、見積りの誤差や赤字工事の温床となっているケースも多く存在します。
● RocoTimeで勤怠=原価情報に変わる理由
| 原価管理の課題 | RocoTimeによる解決 |
|---|---|
| 勤怠と工事原価のデータが分断している | 勤怠データに現場名・工程・作業区分を紐づけ可能 |
| 請求内容と実働データの差異を把握できない | 協力会社単位でも実績を見える化し、照合が容易に |
| 見積り・配員計画に過去データが活かされない | 蓄積された工程別の勤怠データを分析に活用 |
● 現場別・工程別・人別に、労務原価を正確に集計
RocoTimeでは、以下のような管理が可能です。
- 作業員ごとに「何時から何時まで、どの現場・工程で作業したか」を正確に記録
- 原価に直結するデータをCSV形式で即時出力
これにより、従来は属人的・勘頼みだった原価把握を、客観的・定量的に可視化できます。
● “原価を把握するだけ”で終わらせない。次の改善にもつながる
- 赤字工事の発見が「完工後」ではなく「施工中」にできる
- 作業工程別の生産性が見えるため、配置の見直しや多能工育成の判断が可能
- 見積作成時に、過去類似工事の実績データを参照活用
RocoTimeは勤怠情報を「作業の実態」として残すことにより、原価管理の中核データに変換します。単なる打刻記録ではなく、経営判断に使える“指標”を現場から自動で生み出す仕組みとして機能します。
7. 施工体制台帳・安全衛生書類も、勤怠データと連携できる設計

建設業の現場運営においては、施工体制台帳や安全衛生書類の整備と提出が避けて通れません。
これらは単なる形式的な書類ではなく、労働基準監督署や元請との信頼関係を構築するための重要資料です。しかし実態としては、別途のExcelや紙で作成されることが多く、勤怠システムと分断して運用されているケースが多く見受けられます。その結果、「誰がいつどの現場にいたか」「配置人数は適切だったか」といった実績データの整合性にズレが生じ、書類の整合確認や修正作業に時間を要する状況を生んでいます。
● 書類作成を効率化するRocoTimeの連携力
| 課題 | RocoTimeによる対応 |
|---|---|
| 勤怠と台帳情報が連携しておらず整合確認が煩雑 | 勤怠データに現場・職種・作業内容などを紐づけ可能 |
| 書類ごとに別途データ整形・転記が必要 | 台帳・安全書類フォーマットと合致する形でCSV出力できるよう、カスタマイズが可能 |
| 配置人数・稼働実績の確認に時間がかかる | 現場別・日別の作業員実績を地図や一覧で即時確認可能 |
● 他SaaS・基幹システムとの連携にも対応
RocoTimeは、さまざまなクラウドサービス・基幹システムと連携可能です。
【連携対象例】
・給与計算ソフト(PCA、弥生、マネーフォワードなど)
・人事管理システム(SmartHR、COMPANY、人事奉行など)
・プロジェクト・原価管理ツール(自社構築システムや建設業向けSaaSなど)
【連携方法】
・マスタは定期バッチ or 任意取込で柔軟に対応可能
※一部システムにはAPI連携が可能
● 一元管理が、精度とスピードの両立を実現
RocoTimeを中心とした連携により、以下のような業務変化が生まれます。
- 書類作成・整合チェックの手間を最小限に
- 給与計算の誤差が激減し、締め処理が迅速化
- 人事システムとデータが一致するため、評価や労務対応もスムーズに
施工体制台帳、安全衛生書類、そして給与・人事・原価まで ―
勤怠データを核に、周辺業務との連携を自在に構築できるのがRocoTimeの大きな強みです。
現場と管理がつながるという構造を、書類・データ・連携面から実現し、建設業に求められるコンプライアンス対応と業務効率化を同時に支えます。
勤怠管理システム
「働き方改革」時代の勤怠管理
日本の商習慣を網羅したクラウド 柔軟対応でカスタマイズできる!
「勤怠」が変われば、建設業の未来も変わる

1. システムに現場を合わせる時代は終わり。「現場に合う勤怠管理」を
今の勤怠システムに、どこか「合っていない」と感じていませんか?紙台帳・属人運用・月末処理の集中―。それが「当たり前」になっていたとしても、改善できないわけではありません。
RocoTimeは、そんな建設業の“現場のリアル”に応える勤怠管理システムです。
- 現場ごとの就業ルールや契約条件にも柔軟に対応
- 日報・施工台帳との連携も視野に入れた設計
- 原価管理・人事・労務のデータ活用まで視野に入る設計思想
私たちが提供するのは、「ただ打刻できる」システムではありません。
御社の運用にフィットする、建設業に“ちゃんと使える”勤怠管理の仕組みです。
2. まずは、現場の「やりにくさ」から見つめなおしてみませんか?
勤怠は、変えると大きく変わります。記録の精度、現場の負担、集計のスピード、そして経営判断の質まで。もし今の勤怠に少しでも違和感があるなら、それは業務に「仕組み」が合っていないサインかもしれません。
RocoTimeなら、御社の勤怠運用に合わせて「制度」「現場」「経営」すべてのレイヤーで最適化が可能です。
勤怠管理システム RocoTime(ロコタイム)が解決します
業界・業種、社員数の規模を問わず、 日本の商慣習を網羅した 高機能な勤怠管理システムです。
勤怠管理システムの導入をお考えの企業様は、ぜひご相談ください。



